「老後資金のために投資をしようと思っているけど、ETFってどうなんだろう?」
「VOOがリスクも少なくていいって聞くけどよくわからない」
老後資金として投資という言葉はいまの日本では当たり前になってきましたね。
わたしも「貯金以外勝たん!」と思っていましたが、インフレが加速するなか、貯金をしていればOKかというとそうでもない。
「米国ETF」は分配金ももらえて、なおかつ長期的に見ればリスクも低いと言われていますが実際よくわからないという方が大半だと思います。
そんな方のためにこの記事では
- 米国ETF VOOとはなにか
- VOOを買う際のメリット・デメリット
- 他の投資商品との比較
について解説していきます。
それでは、ぜひ最後までお読みください!
※注意:この記事は投資勧誘を目的とするものではありません。投資は自己判断でお願いします。
米国ETF VOOとは
はじめにETFやVOOとはなにか?基本的な説明からしてきますね。
そもそもETFとはなんなのか
まず知らない方のために「ETF(イーティーエフ)」の説明からしていきます。
ETFとは =「Exchange Traded Fund」の略で上場投資信託のことです。
難しいですね......
かんたんにいうと、証券取引所で取引される投資信託のことです。
「投資信託とのちがいはなに?」と思った方もいるかもしれないですが、
- 上場しているか
- いつでも売買が出来るか
大きな違いは上記の2つだけです。
VOOはS&P500に連動するETF
次にVOOの説明をしていきますね。
以下の表をご覧ください。
ETF銘柄名称 | Vanguard 500 Index Fund ETF |
連動指数 | S&P 500 TR |
基準価格 | 411.07ドル(2022/02/07) |
分配金回数/年 | 4 |
分配金利回り | 1.32% |
経費率 | 0.03% |
補足:S&P500 = 米国企業の中で流動性がある大型株500銘柄の時価総額を指数化したもの
構成銘柄
構成銘柄は米国の主要業種を代表する大型株500銘柄。
上位に入っている銘柄を5つをご紹介します。
こちらも以下の表をご覧ください。
| 順位 | 銘柄名 | 比率 |
|---|---|---|
1 | APPLE INC ORD(アップル) | 6.83% |
2 | MICROSOFT CORP ORD(マイクロソフト) | 6.23% |
3 | AMAZON.COM INC ORD(アマゾン) | 3.59% |
4 | ALPHABET INC CLASS A ORD(アルファベット) | 2.15% |
5 | TESLA INC ORD(テスラ) | 2.12% |
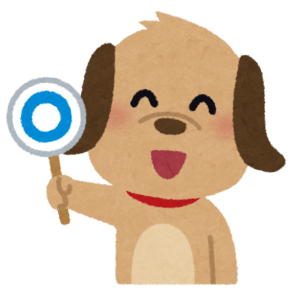
有名な企業ばかりで安心感がありますね。
分配金は?
2021年の分配金をみてみましょう。
保有している株数 × 分配金が入金される金額になります。
ただ、税金を引かれるので実際はもっと少ない金額になってしまいますが......。
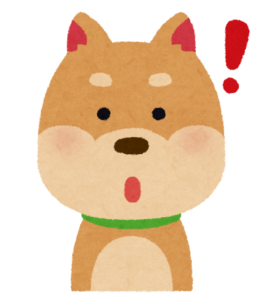
1株持ってたら1年で約5000円もらえるね!
米国ETF VOOの3つのメリット
VOOに投資するメリットはなにか順番にみていきましょう!
- 経費率が低い
- 長期的に成長が期待できる
- 分散投資ができる
1.経費率が低い
VOOの経費率はわずか0.03%(年率)です。
純資産 × 0.03% ÷ 365日 = 1日にかかる経費
年間100万円を運用しても1年でかかる経費は約300円。
価格の変動が大幅にあったとしてもだいぶ安い金額です。
以下の表のように、他のS&P500のETFと比べてみても一目瞭然。
| 銘柄 | 経費率 |
|---|---|
VOO | 0.03% |
QQQ | 0.20% |
SPY | 0.09% |
2.長期的に成長が期待できる
以下の画像は10年間のチャートを示したものです。
コロナの影響で2020年ごろに一度ドカンと下がっていますが、それ以外は長期的に見ると右肩上がりなのがみてわかると思います。
米国経済が成長を続けていけば、今後も同じように上昇していくと思われます。
あくまでも投資は自己責任でお願いします。
3.分散投資ができる
VOOに限らずですが、ETFを1株購入するだけで多くの構成銘柄へ投資ができるので、リスクを分散することが可能です。
S&P500と連動しているVOOは、米国の主要業種を代表する大型株500銘柄に分散投資できるので、初心者には特にメリットとなる部分だと思います。
米国ETF VOOの3つのデメリット
デメリットは以下の3つです。こちらも順番に解説していきます!
- 日米での二重課税
- 基準価格が高く資金が必要になる
- 分配金利回りが低め
1.日米での二重課税
投資にかかる税金ってすごい高いですよね。
分配金には日米合わせて約30%の税金が差し引かれます。
詳細は以下のとおり。
- 米国税 10%
- 日本税 20.315%
しかし、米国税に関しては、確定申告で取り戻すことができます。
わたしはやったことがありませんが......
少額なので米国税といっても、引かれているのは数百円なので「まぁいっか」となってしまうのが本音。
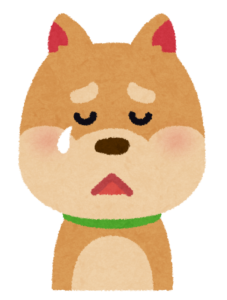
確定申告の手間を考えると「めんどくさい」の方が大きいんです。
2.基準価格が高く資金が必要になる
投資信託と違って、ETFは1株からの買付となります。
基準価格が高い場合は資金力が必要です。
特にVOOの場合は、2022年2月7日の基準価額は411.07USドル。
1株買うにも日本円で約47,000円も必要になります。(※1ドル115円計算)
また、資金が少ないと「ドル・コスト平均法」も活用できず、ただの定額購入となってしまいます。
毎月買い増しをするのであれば約20万〜は確保したいところですね。
ドルコスト平均法とは=価格が変動する商品に対して「常に一定金額を、定期的」に購入する方法です。投資金額を一定にすることで、価格が低いときには購入量(口数)が多く、価格が高いときには購入量(口数)が少なくなり、平均購入単価を抑えることが期待できます。
三井住友銀行
3.分配金利回りが低め
他のETFと利回りの比率を比較してみました。
以下の表をご覧ください。
| 銘柄 | 配当比率 |
|---|---|
VOO | 1.32% |
VYM | 2.74% |
VTI | 1.30% |
SPYD | 3.57% |
HDV | 3.37% |
高配当のETFと比べると利回りは低めです。
ただ、同じS&P500と連動しているETFと比べるとあまり大差は無いため、ずば抜けて低いとは言い難いところです。
米国ETF VOOを取り扱っている証券会社
VOOを取り扱っている証券会社は以下の通りです。
VOOは人気のETFなので取り扱える証券会社が多いようですね。 わたしはこの中でもSBI証券と楽天証券を併用しています!
SBI証券は自動で積立投資ができるからおすすめ。
楽天証券は何といってもみやすくて操作のしやすさがダントツです。
米国ETF VOOへの投資方法
投資方法は以下の3つがあります。
- 現物
- CDF取引
1.現物
まずは現物。
現物というのは現金で株を買い、保有するということ。
購入する時はドルで買うのか、円で買うのかを選ぶ必要があります。
今は証券会社でも購入する手数料が、あまりかからないようなので円で購入するのもありです!
楽天証券の場合は為替手数料が(片道25銭/ドル)かかります。
わたしは分配金がドルで入金されてくるため、いつもドルで購入してしまいます。

最近円安も進んでいるので、なるべくドルも確保していたい......。
2.CFD取引
2つ目はCFD取引。聞き慣れませんよね。
CFD = Contract For Differenceの頭文字を取ったもので「差金決済取引」というものです。
取引を行ったことにして、売買したあとの損益の差額のみ取引するというやり方。
初心者向けでは無いためここでは説明を省かせていただきます。
VOOを他の投資商品と比較!
ETFもたくさんあるため「ほんとうにETFならVOOが最適なの?」「ETFよりも投資信託の方がいいんじゃないの?」という疑問もあると思うのでVOOと比較する形で順番に解説していきますね!
- VTI、QQQとの比較
- ETF or 投資信託
1.VOOをVTI、QQQと比較
VOO、VTI、QQQともに上位構成銘柄にハイテク株(GAFAM)が組み込まれています。
補足
GAFAMとは = グーグル、アマゾン、フェイスブック、アルファベット(グーグル)、マイクロソフトのこと
| 銘柄 | VOO | VTI | QQQ |
|---|---|---|---|
運用会社 | バンガード社 | バンガード社 | インベスコ |
連動指数 | S&P500 | CRSP US Total Stock Market | NASDAQ100 |
配当金(分配金)利回り | 1.32% | 1.30% | 0.47% |
構成銘柄数(約) | 500 | 3500 | 100 |
5年のトータルリターン | 16.79% | 16.19% | 24.55% |
上記の表で見ると、配当金(分配金)利回りは「VOO」の1.32%がいいのに対し、5年のトータルリターンの比率は「QQQ」の24.55%が圧倒的なのがわかります。
これにより、配当金(分配金)を目的とするのであれば「VOO」、キャピタルゲインを目的とするのであれば「QQQ」を選べばいいということがわかりますね。
補足
キャピタルゲイン = 株の売却によって得られる利益のこと
2.ETFか投資信託はどっちを買った方がいいの?
2つめの「ETFか投資信託はどっちを買った方がいいの?」という疑問については、結論からいうと「初心者なら投資信託の方が始めやすい」と思います。
投資信託はつみたてNISAで非課税の範囲で始めることも可能です。
つみたてNISAの始め方は以下の記事で紹介しています。
デメリットでも前述したとおり、ETFは投資信託とちがい少額からの投資ができず、基本的には1株100ドルを超えるものばかりです。
まずは投資信託で慣れてから、ETFも併用して運用していく方法が一番いいと思います。
ETFと投資信託では、どちらが優れている、どちらが劣っているという訳ではありません。どういうスタンスで資産運用を考えるかで選択する、場合によっては両方を組み合わせるなどを考えてみるのも良いでしょう。
日本証券業協会
まとめ:米国ETF VOOは良くも悪くもリスクが少ない
最後に要点だけまとめると以下の通りです。
VOOのメリットは
- 経費率が低い
- 長期的に成長が期待できる
- 分散投資ができる
VOOのデメリットは
- 日米での二重課税
- 基準価格が高く資金が必要になる
- 分配金利回りが低め
VOOは他のETFと比べてもそこまで大差がなく、経費率も悪く無いためリスクは最小限で投資ができるといえます。
ただ、資金力が必要になるので初心者の方は少額から始められる投資信託から始めてみるのもおすすめです。

.jpg)
.jpg)
